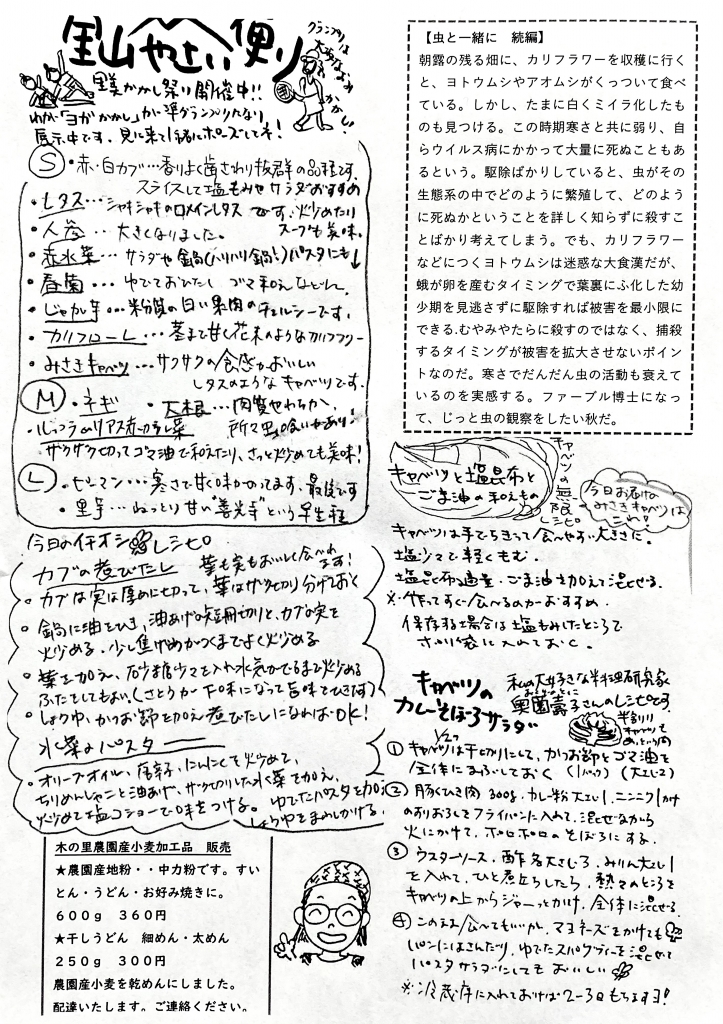
野菜便り2020/11/6
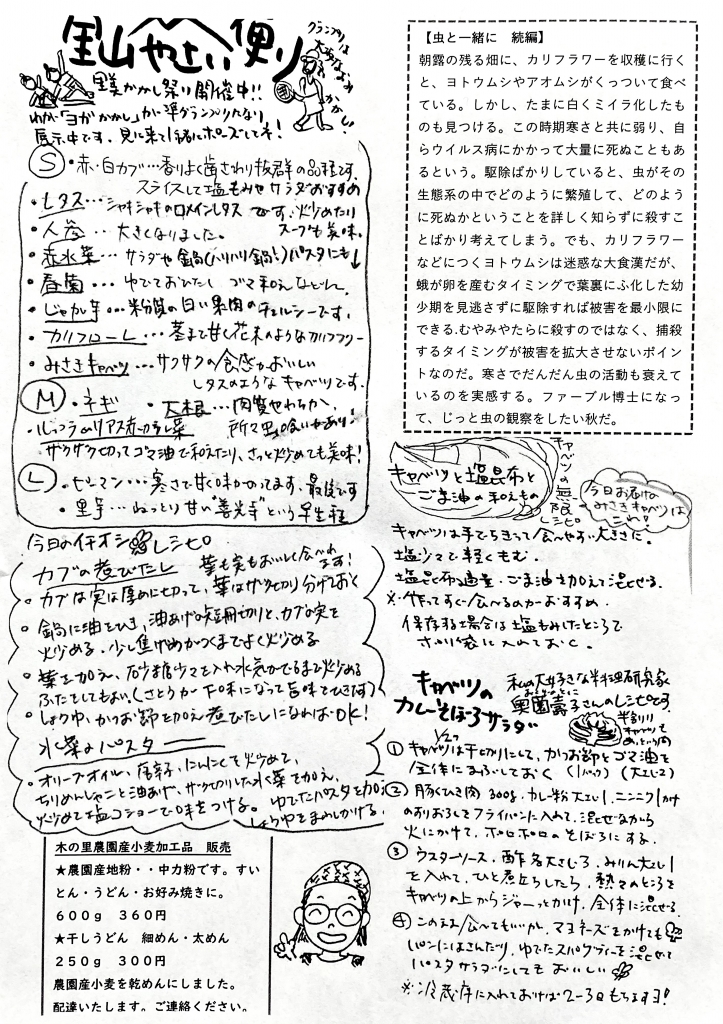
by 木の里農園
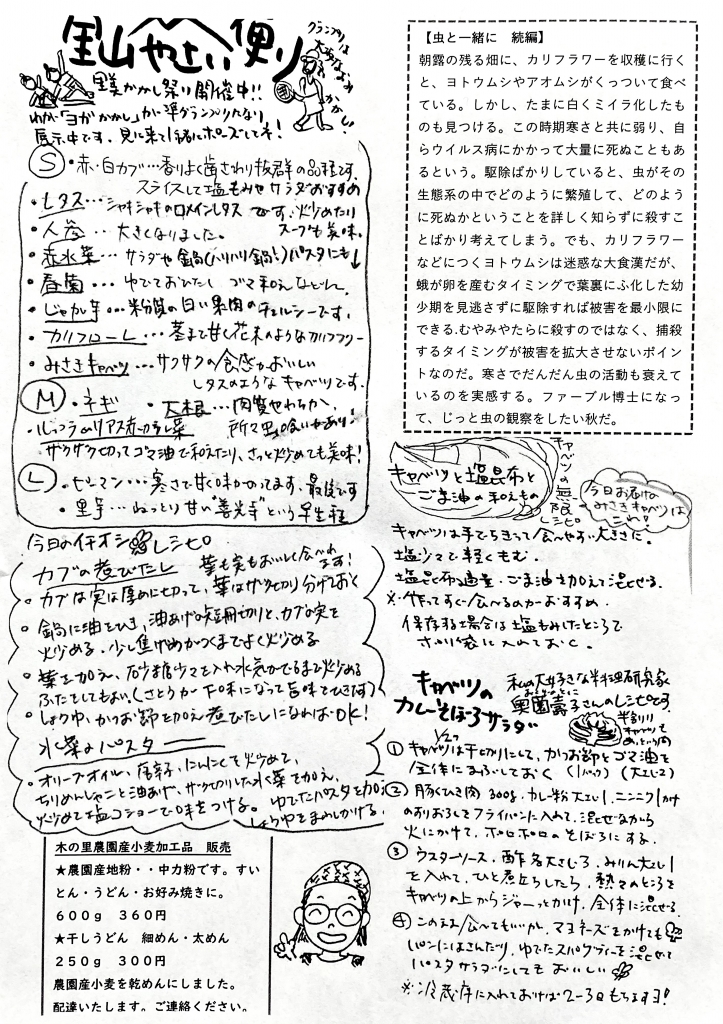
by 木の里農園

 ハウスのミニトマトも色づき始まりました。毎日せっせと潅水しています。また、今年から新たに雨よけハウスを2棟建設して、1棟でパプリカ、もう1棟でイタリアントマトを作付けしています。ミニトマトは来週あたりから。イタリアントマトは8月からお届け予定です。
ハウスのミニトマトも色づき始まりました。毎日せっせと潅水しています。また、今年から新たに雨よけハウスを2棟建設して、1棟でパプリカ、もう1棟でイタリアントマトを作付けしています。ミニトマトは来週あたりから。イタリアントマトは8月からお届け予定です。

 バジルも色々ありますので、ほしい方はご連絡くださいね。
バジルも色々ありますので、ほしい方はご連絡くださいね。
 こちらは露地で育てているピーマン類。
こちらは露地で育てているピーマン類。
 そして、みなさまお待たせしました!夏の役者、枝豆の「湯上り娘」今週からお届けです。ズッキーニが夏バテした後に控えるコリンキーも、少しずつ膨らんでおります。
そして、みなさまお待たせしました!夏の役者、枝豆の「湯上り娘」今週からお届けです。ズッキーニが夏バテした後に控えるコリンキーも、少しずつ膨らんでおります。

 今年初めて作った「食べきりバターナッツ」。やたらと成っています。若採りしてズッキーニのようにも食べられるとか。楽しみです。右は今が盛りのキュウリの花です。今年はミツバチがすごく少ないのですが、早くも出荷しきれないくらいの収穫に追われています。
今年初めて作った「食べきりバターナッツ」。やたらと成っています。若採りしてズッキーニのようにも食べられるとか。楽しみです。右は今が盛りのキュウリの花です。今年はミツバチがすごく少ないのですが、早くも出荷しきれないくらいの収穫に追われています。

 バジルと青シソ。
バジルと青シソ。
 ツルムラサキ(手前)と空心菜2番手(奥)。
ツルムラサキ(手前)と空心菜2番手(奥)。 野菜を育てる土に無理をかけないように、毎年30アールほどでホウキモロコシを育てて、1年間完全に畑を休ませています。育てた草は、東京の箒職人さんが刈り取って、手作り箒に生まれ変わります。私も少しは作ります。。。木の里農園の農業を通じて、日本の伝統的な手仕事のお手伝いができるのは、大きな喜びでもあります。
野菜を育てる土に無理をかけないように、毎年30アールほどでホウキモロコシを育てて、1年間完全に畑を休ませています。育てた草は、東京の箒職人さんが刈り取って、手作り箒に生まれ変わります。私も少しは作ります。。。木の里農園の農業を通じて、日本の伝統的な手仕事のお手伝いができるのは、大きな喜びでもあります。
 そしていよいよじゃがいも掘り始まります。左上から時計回りにチェルシー・サッシー・ノーザンルビー・キタアカリ・シャドークイン・アローワ・グランドペチカ。今年はこのラインナップでお届けします。
そしていよいよじゃがいも掘り始まります。左上から時計回りにチェルシー・サッシー・ノーザンルビー・キタアカリ・シャドークイン・アローワ・グランドペチカ。今年はこのラインナップでお届けします。
 先日の満月の夕暮れ。日中汗にまみれて働いて、陽が落ちてから飲むビールは最高であります(笑)
先日の満月の夕暮れ。日中汗にまみれて働いて、陽が落ちてから飲むビールは最高であります(笑)

by 木の里農園
 いよいよ2月も終わり、弥生3月がやってきました。卒業や入学、就職や引っ越しなど、一年で人が最も動く季節でもあります。農園でも夏野菜の種まきが一気に始まって、日差しも力を増して、私達も大地が目覚めるリズムを少しずつ先取りしながら、畑に作物を植え付けてゆきます。
一方で、お届けする畑の野菜は一年で最も少なくなる季節です。長い冬の食卓を支えてくれた冬野菜が終わり、畑に残った野菜は一斉に花を咲かせます。そうです、野菜の端境期がやってきてしまいました。
有難いことに、そんな季節にも関わらず、新規のお問い合わせやお申し込みを数多く頂いております。しかし、3月と4月はいったん新規の方への発送をストップさせていただきます。そのうえで、今食べてくださっている方へのお届けに全力で集中したいと思います。
なお、この期間にお申込みいただいた方には、5月以降優先的にご案内を差し上げますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
いよいよ2月も終わり、弥生3月がやってきました。卒業や入学、就職や引っ越しなど、一年で人が最も動く季節でもあります。農園でも夏野菜の種まきが一気に始まって、日差しも力を増して、私達も大地が目覚めるリズムを少しずつ先取りしながら、畑に作物を植え付けてゆきます。
一方で、お届けする畑の野菜は一年で最も少なくなる季節です。長い冬の食卓を支えてくれた冬野菜が終わり、畑に残った野菜は一斉に花を咲かせます。そうです、野菜の端境期がやってきてしまいました。
有難いことに、そんな季節にも関わらず、新規のお問い合わせやお申し込みを数多く頂いております。しかし、3月と4月はいったん新規の方への発送をストップさせていただきます。そのうえで、今食べてくださっている方へのお届けに全力で集中したいと思います。
なお、この期間にお申込みいただいた方には、5月以降優先的にご案内を差し上げますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
by 木の里農園
 でも、ハウスの中はこんな感じで緯度が5度ほど低くて、朝からでも収穫できます。主にサラダ系の葉物類を育てているので、僕はこの収穫に取り掛かります。ルッコラ・赤水菜・わさび菜・リーフレタス等をひと種類ずつ収穫してゆきます。結構時間がかかります。
でも、ハウスの中はこんな感じで緯度が5度ほど低くて、朝からでも収穫できます。主にサラダ系の葉物類を育てているので、僕はこの収穫に取り掛かります。ルッコラ・赤水菜・わさび菜・リーフレタス等をひと種類ずつ収穫してゆきます。結構時間がかかります。
 収穫を終えて戻ると、出荷場は佳境に入っていて、僕がつけ入るスキがない。。。(苦笑)
収穫を終えて戻ると、出荷場は佳境に入っていて、僕がつけ入るスキがない。。。(苦笑)
 カブが袋詰めされていました。今回は、黄金カブ・白馬かぶ・あやめ雪カブなどのミックスです。
カブが袋詰めされていました。今回は、黄金カブ・白馬かぶ・あやめ雪カブなどのミックスです。
 基本的に僕は収穫担当で、出荷場に居場所はありません。そそくさと隅っこにコンテナを並べて、朝から収穫したサラダ野菜の袋詰めをもくもくと。。。って、もう昼だしっ‼
基本的に僕は収穫担当で、出荷場に居場所はありません。そそくさと隅っこにコンテナを並べて、朝から収穫したサラダ野菜の袋詰めをもくもくと。。。って、もう昼だしっ‼
 お昼前までにSサイズの箱詰めを終わらせるべく、全員ほぼトランス状態で作業に集中します。たまに聞こえるのは連絡や確認などの短い会話だけです。
で、何とか箱詰めが終わりました。今週のSサイズの中身は、、、長ねぎ・白菜・人参・ターツァイ・大根・里芋・ごぼう・サラダ野菜ミックス(ルッコラ・わさび菜・赤水菜・オークリーフ・ロメインレタスなど)・オプションで林平さんのシイタケ、まったり~村の卵などでした。
お昼前までにSサイズの箱詰めを終わらせるべく、全員ほぼトランス状態で作業に集中します。たまに聞こえるのは連絡や確認などの短い会話だけです。
で、何とか箱詰めが終わりました。今週のSサイズの中身は、、、長ねぎ・白菜・人参・ターツァイ・大根・里芋・ごぼう・サラダ野菜ミックス(ルッコラ・わさび菜・赤水菜・オークリーフ・ロメインレタスなど)・オプションで林平さんのシイタケ、まったり~村の卵などでした。
 お昼ご飯を済ませて、午後はM.Lサイズの箱詰めをして、野菜が傷まないようにレイアウトなど確認してからお便りを入れて封をして、発送準備完了です。ふうう~(^^)
あとは、16時前にクロネコさんが集荷に来てくれて送り出し、その後近隣向けの配達に出ます。僕は午後の出荷作業からは抜けて、配達に出るまでの貴重な数時間を使って畑仕事です。そして配達から帰るのは20~21時。長い2日間が終わりました。でも、宅急便の到着は翌日。皆様のもとに無事に着くまでは、やはり心配なものです。
農園の野菜を食べてくださる方もじわじわと増えてきて、そろそろこのメンバーだけで出荷業務を回すのは限界になってきました。今年は一緒に仕事してくれるメンバーを探そうと思っています。事業拡大のためというよりは、むしろ今の仕事をより楽しく、より充実させて、野菜に反映させてゆくためのメンバーです。一戸建ての宿舎もあるので遠方の人でも大丈夫。
というわけで、最後に少し話が逸れましたが、真冬の野菜ボックス作りのお話を終わります。
お昼ご飯を済ませて、午後はM.Lサイズの箱詰めをして、野菜が傷まないようにレイアウトなど確認してからお便りを入れて封をして、発送準備完了です。ふうう~(^^)
あとは、16時前にクロネコさんが集荷に来てくれて送り出し、その後近隣向けの配達に出ます。僕は午後の出荷作業からは抜けて、配達に出るまでの貴重な数時間を使って畑仕事です。そして配達から帰るのは20~21時。長い2日間が終わりました。でも、宅急便の到着は翌日。皆様のもとに無事に着くまでは、やはり心配なものです。
農園の野菜を食べてくださる方もじわじわと増えてきて、そろそろこのメンバーだけで出荷業務を回すのは限界になってきました。今年は一緒に仕事してくれるメンバーを探そうと思っています。事業拡大のためというよりは、むしろ今の仕事をより楽しく、より充実させて、野菜に反映させてゆくためのメンバーです。一戸建ての宿舎もあるので遠方の人でも大丈夫。
というわけで、最後に少し話が逸れましたが、真冬の野菜ボックス作りのお話を終わります。
by 木の里農園
 次に、畑がまだ凍っているうちに根菜類の掘り出しをします。真冬の朝から午前中にかけては、土や野菜が凍っていて、特に葉物類の収穫ができません。なので、まずは根菜類をガシガシ掘り出してゆきます。
大根。種まきの時期や栽植密度を微調整して、野菜ボックスに合う、コンパクトなサイズに仕上げます。それでもデカくなっちゃう暴れんぼ君は給食センター行きです。大きさを選別しながらコンテナに詰めます。
次に、畑がまだ凍っているうちに根菜類の掘り出しをします。真冬の朝から午前中にかけては、土や野菜が凍っていて、特に葉物類の収穫ができません。なので、まずは根菜類をガシガシ掘り出してゆきます。
大根。種まきの時期や栽植密度を微調整して、野菜ボックスに合う、コンパクトなサイズに仕上げます。それでもデカくなっちゃう暴れんぼ君は給食センター行きです。大きさを選別しながらコンテナに詰めます。
 長ねぎ。土もネギもガチガチに凍っています。ツルハシを使って凍り付いた土を慎重にネギからはがして、そおっと抜きます。
長ねぎ。土もネギもガチガチに凍っています。ツルハシを使って凍り付いた土を慎重にネギからはがして、そおっと抜きます。
 そのまましばしの日光浴で解凍の儀。
そのまましばしの日光浴で解凍の儀。
 で、その間に人参の掘り出し。こちらもとにかく土が凍りついてるのでツルハシを振り回します(笑)
で、その間に人参の掘り出し。こちらもとにかく土が凍りついてるのでツルハシを振り回します(笑)
 他にも赤カブやら色大根やらカラー人参やらと根菜類を掘りまくっているうちに、あっという間に昼です。
午後の陽は短いので、昼ごはんもそこそこに今度は葉物類の収穫です。まずは山の畑の小松菜から。農園で最も寒い畑で、今日は小松菜の収穫です。下葉の掃除が冬は何倍も時間がかかって、あっという間に陽が傾いてきて、少し焦ります。
他にも赤カブやら色大根やらカラー人参やらと根菜類を掘りまくっているうちに、あっという間に昼です。
午後の陽は短いので、昼ごはんもそこそこに今度は葉物類の収穫です。まずは山の畑の小松菜から。農園で最も寒い畑で、今日は小松菜の収穫です。下葉の掃除が冬は何倍も時間がかかって、あっという間に陽が傾いてきて、少し焦ります。
 葉物類は収穫したらすぐに出荷場に届けて、妻とパートさんがすぐに袋詰めです。出荷場では午前中に掘りあげた根菜類の洗い作業をしていました。今年から、大根やカブ、人参等、冬の葉を切ってお届けする期間中は、すべて泥を洗うことに致しました。
赤カブ
葉物類は収穫したらすぐに出荷場に届けて、妻とパートさんがすぐに袋詰めです。出荷場では午前中に掘りあげた根菜類の洗い作業をしていました。今年から、大根やカブ、人参等、冬の葉を切ってお届けする期間中は、すべて泥を洗うことに致しました。
赤カブ
 色大根いろいろ。普通の青首大根も「人参洗い機」で洗います。機械なので手加減をしてくれません。水量と洗いをやめる(スイッチを切る)タイミングに神経を使います。
色大根いろいろ。普通の青首大根も「人参洗い機」で洗います。機械なので手加減をしてくれません。水量と洗いをやめる(スイッチを切る)タイミングに神経を使います。
 女性陣は出荷場を切り盛りしてくれているので、僕は小松菜を届けてからすぐに白菜の収穫に。
この黒いネットの下に。。。
女性陣は出荷場を切り盛りしてくれているので、僕は小松菜を届けてからすぐに白菜の収穫に。
この黒いネットの下に。。。
 白菜が囲ってあります。わざと遮光(4重被覆)して半凍結状態にすることで、傷みを抑えています。でも、今年は小ぶりだなあ。。。
白菜が囲ってあります。わざと遮光(4重被覆)して半凍結状態にすることで、傷みを抑えています。でも、今年は小ぶりだなあ。。。
 さらに、午前中の畑に戻って、夕日と競争でトンネル栽培の小かぶを収穫。強風でトンネルが吹っ飛びそうですな。あっ、右側の2重トンネルには、昨日大根類、人参類、サラダカブの種まきをしました。
さらに、午前中の畑に戻って、夕日と競争でトンネル栽培の小かぶを収穫。強風でトンネルが吹っ飛びそうですな。あっ、右側の2重トンネルには、昨日大根類、人参類、サラダカブの種まきをしました。
 そして最後にようやくターツァイの畑に到着。このところの寒波でどんどん縮んでいるんでバリバリ収穫です。
そして最後にようやくターツァイの畑に到着。このところの寒波でどんどん縮んでいるんでバリバリ収穫です。
 や、やばい、、陽が沈む~‼
や、やばい、、陽が沈む~‼
 この時期は、陽が沈むのと同時に野菜類は表面からバリバリ凍結してゆきます。日暮れと凍結と競争しながら収穫と掃除を畑でやっちゃいます。靴はスノーブーツ。頭にネックウォーマーを巻いた上からジャンパーのフードをかぶって防寒は完璧ですが、手先は素手じゃないと葉物を扱えません。最後はヘッドランプを灯して。大体終了は18時ころ。
出荷場に持ち帰り、保冷庫等に今日収穫調整した野菜をしまって、出荷前日の畑作業は終了です。
続きはまた後日。次は出荷当日編をお楽しみに!
この時期は、陽が沈むのと同時に野菜類は表面からバリバリ凍結してゆきます。日暮れと凍結と競争しながら収穫と掃除を畑でやっちゃいます。靴はスノーブーツ。頭にネックウォーマーを巻いた上からジャンパーのフードをかぶって防寒は完璧ですが、手先は素手じゃないと葉物を扱えません。最後はヘッドランプを灯して。大体終了は18時ころ。
出荷場に持ち帰り、保冷庫等に今日収穫調整した野菜をしまって、出荷前日の畑作業は終了です。
続きはまた後日。次は出荷当日編をお楽しみに!
by 木の里農園
 そもそも有機農法というものは、土作りや自然のシステムを生かす方法であり、本来気候変動や異常気象には強いと言われています。しかし、どんなに優れた技術や土壌があったとしても、その土台には太陽からの日照がある。そこは痛感しました。じゃあ今のうちの野菜供給を支えているものは何か?それはとにかく毎日やみくもに様々な作物の種を播き、植え付けてきたこと。。。。。つまり多品目栽培にあると言えます。リスク分散ですね。
生産効率を無視したこの手法こそが皆さんの日々の食卓を支えているのです(笑)その根底を突き詰めてゆくと、それは「売るために作る」のではなくて、「食べるために作る」という、私たちの永遠のアマチュアリズムがあるのかも知れません。
でも本当はやはりこういう安易な結論じゃなくて、気候変動にも揺るがない、しっかりと作物の成長を支え続けられる農業者でありたいものです。決して偉そうに言える話でもないので、今日はこの辺で。今は冬から春に向けての畑の準備と種まきに追われています。
半年後を見越した作付と(半年後に後悔しない!)、もっと大きな流れの中での土を見つめること。
まだまだ勉強してゆきたいです。
そもそも有機農法というものは、土作りや自然のシステムを生かす方法であり、本来気候変動や異常気象には強いと言われています。しかし、どんなに優れた技術や土壌があったとしても、その土台には太陽からの日照がある。そこは痛感しました。じゃあ今のうちの野菜供給を支えているものは何か?それはとにかく毎日やみくもに様々な作物の種を播き、植え付けてきたこと。。。。。つまり多品目栽培にあると言えます。リスク分散ですね。
生産効率を無視したこの手法こそが皆さんの日々の食卓を支えているのです(笑)その根底を突き詰めてゆくと、それは「売るために作る」のではなくて、「食べるために作る」という、私たちの永遠のアマチュアリズムがあるのかも知れません。
でも本当はやはりこういう安易な結論じゃなくて、気候変動にも揺るがない、しっかりと作物の成長を支え続けられる農業者でありたいものです。決して偉そうに言える話でもないので、今日はこの辺で。今は冬から春に向けての畑の準備と種まきに追われています。
半年後を見越した作付と(半年後に後悔しない!)、もっと大きな流れの中での土を見つめること。
まだまだ勉強してゆきたいです。